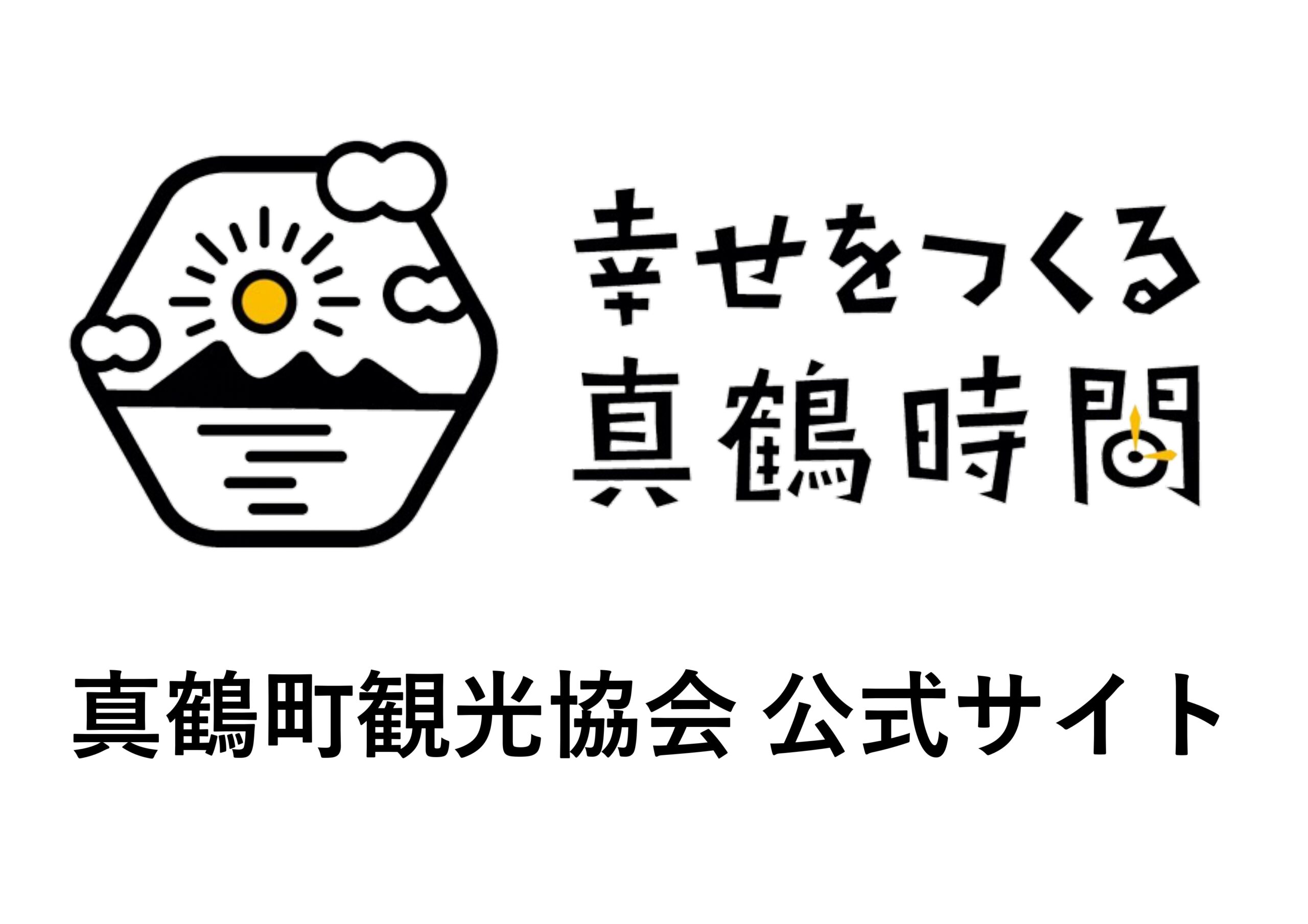夏目漱石の「真鶴行」は漱石晩年の大正5年、短編小説の形を執った未発表の小品である。漱石は隣の湯河原村から軽便鉄道に乗り、真鶴村の城口停車場で下車。旅館までの風景や出来事、食事風景を描写し、ブリ漁の船に乗り漁の様子を描いた短編である。その当時の村の様子が手に取るように分かる歴史的資料である。
冒頭にこんなくだりがある。➡門川まで歩く。田舎道で荷を肩にした肴屋ニ会フ。「旦那方はどちらに御出でです」「真鶴ですか。そう遠くはありません。」(略)「好い所かへ」「ええ揚屋が十軒あります」「外に何もないかね」「もう少し早いとブリ網が見られるでしょう」・・・・
揚屋を辞書で引くと、遊里で遊女屋から遊女を呼んで遊ぶとある。
海路、江戸と直結した真鶴村は小江戸とも呼ばれ船宿、お茶屋が盛況を極めた。江戸城構築のための石材業やブリ漁が隆盛を極め村は活況を呈していた。漱石も漁師との会話で書いている。「大漁の時は七万位ブリがかかるんですから、まあ十万円近くの金になるんです。一人が一晩に二十とか三十という金を懐に入れますがそれをみんな飲んじゃいます」「それで揚屋が必要なんだね」と。
真鶴村では揚屋で働く茶屋女を三崎女郎のような「じゃりそば」と呼んだ。熱海でも呼んでいたと、舟橋聖一著、風流抄の中で書かれている。じゃりそばとは、じゃれるそば女の転訛したものだという説もあり。
真鶴町の現在は、歴史の中でも一番低迷している時代と言える。だが、真鶴人の江戸っ子気質は受け継がれ、適度な好色と適度なずぼらさがこの町の魅力だと私は思っている。